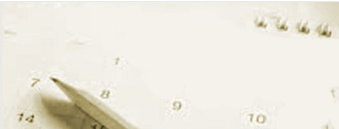バーレーン訪問を振り返る、教皇一般謁見
教皇フランシスコは、11月9日、バチカンの聖ペトロ広場で、水曜日恒例の一般謁見を行われた。
謁見中、教皇は、先日行われたばかりのバーレーン司牧訪問(11月3日‐6日)を振り返った。
教皇の講話の要旨は次のとおり。
**********
バーレーン王国の訪問から戻り、この訪問を祈りによって支えてくださった皆さん、大変温かくもてなしてくださった国王をはじめ同国当局と教会そして国民の皆さん、そしてわたしの訪問がスムーズに運ぶよう多大な仕事をしてくださった関係者らに心からのお礼を申し上げたい。
なぜ教皇はイスラム教徒が大部分を占めるこの小さな国を訪れることを望んだのか、という疑問がおのずとわくことだろう。この問いに、「対話」「出会い」「歩み」という3つの言葉を通して答えたい。
「対話」:この訪問のきっかけは、東洋と西洋の人類の共存を主題とする「対話のためのバーレーン・フォーラム」にバーレーン国王から招きを受けたことであった。
他の人々や、宗教、伝統が持つ豊かさを発見するためには、対話が必要である。様々な島からなる列島バーレーンは、生きるためには孤立ではなく、歩み寄ることが大切であると教えてくれる。対話は平和のために必要であり、対話は「平和のための酸素」である。
およそ60年前、第2バチカン公会議は、平和の構築には、国家的なエゴイズムや他国に対する優越などの野心を捨て、国を超え、全人類に対する深い尊重を育みつつ、精神と心を広げる必要があると説いた。
バーレーンではこのような必要を感じ、全世界の宗教者や社会の責任者らが自分の共同体の枠を超えた、全体を心にかけるために、自らの境界線の外を見るを力を養うことを願った。こうしてこそ、神の忘却や、飢餓の悲劇、自然保護、平和などの普遍的なテーマと対峙することができる。
「対話のためのバーレーン・フォーラム」は、出会いの道を選択し、衝突を拒むことを奨励するものであった。わたしたちはこれをどれほど必要としていることか。戦争の狂気の犠牲者であるウクライナをはじめ、他の多くの紛争も、幼稚な武力の論理ではなく、対話の穏やかな力を通してこそ解決できるだろう。
「出会い」:しかし、出会いなくして対話はない。バーレーンでは様々な出会いがあり、そこではキリスト教とイスラム教間の出会いと関係の強化を望む声が聞かれた。
バーレーンでは、誰かに挨拶する時、手を胸にあてる。わたしも同じようにすることで、出会う人に心を開こうとした。相手を受け入れることがなければ、その対話は現実ではなく理想だけの虚しいものになるからである。
多くの出会いの中には、愛する兄弟、アル=アズハル・モスクのグランド・イマームや、カトリック学校での若者たちとの出会いもあった。そこで生徒たちはキリスト教徒もイスラム教徒も一緒に勉強していた。早くから互いを知ることが大事であり、このような兄弟的出会いは、イデオロギーによる分裂を予防するものである。
「イスラム長老評議会」は、数年前に生まれた国際組織であるが、イスラム共同体間の良好な関係を推進し、原理主義や暴力に反対しながら、尊重、中庸、平和を教えている。
「歩み」:バーレーンへの旅は、単独の出来事ではなく、聖ヨハネ・パウロ二世がモロッコを訪問して以来の一続きの歩みとして捉えられるべきである。教皇によるバーレーン初訪問は、キリスト教とイスラム教の歩みにおける新たな一歩を表している。
その歩みは互いを混同したり、信仰をうすめるためのものではない。それは父祖アブラハムの名において兄弟的な絆を築くためのものである。アブラハムは唯一の天の神、平和の神のいつくしみの眼差しのもとに地上を巡礼した。それゆえ、この訪問は「地には平和、御心に適う人にあれ」をモットーとしていた。
バーレーンにおける「対話、出会い、歩み」は、キリスト者間においても行われた。そこでは兄弟であるバルトロメオス一世総主教をはじめ、キリスト教の諸教会や様々な典礼の人々との出会いがあった。
また、バーレーンのカトリック信者たちは、まさに「歩み」を生きていた。彼らの多くは故郷を離れ、移民となって働きながら、神の民としてのルーツ、教会という大きな家族を再発見した人々である。
司牧者や修道者などカトリック教会関係者らとの出会いや、湾岸諸国の多くの信者たちと祝った感動的なミサの中で、わたしは彼らに全教会からの愛情を伝えた。そして、今日、わたしは彼らの純粋で素直で美しい喜びを皆さんに伝えたい。
兄弟愛と平和の歩みを進めるには、すべての人、一人ひとりの力が必要である。聖母がこの歩みを助けてくださいますように。